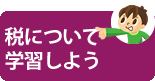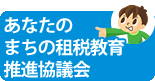「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」
これは、「日本国憲法第30条」に書かれている、税についての決まりです。
税は、およそ一七八〇年もの昔、卑弥呼の時代からありました。その頃は、税として食べ物が納められていたそうです。その後はそれに加え、地域の特産品や労働が税として納められるようになりました。また、農民だけでなく、町人にも税が課せられるようになりました。明治時代には、税を年貢ではなく、貨幣で納めるようになりました。大正時代になると、現在の税金の基本となる仕組みや法律ができ、平成元年からは、消費税が施行されています。
私ははじめ、なぜ税金を納めなければならないのか、いつも不思議でなりませんでした。しかし、どんどん調べていくうちに、私は税にまつわる、2つのエピソードを見つけました。これらのエピソードを例に、なぜ税が必要なのか、考えてみたいと思います。
まず1つ目は、「双方一致の上、相談を取極めたり。これ即ち政府と人民の約束なり。」という言葉です。これは、福澤諭吉さんの、「学問のすすめ」に書かれている文です。訳すると、「これは政府と国民双方が一致した約束である。」ということ。私は、税金が国民と国との約束であるということを初めて知ることができました。
2つ目は、"No taxation without representation"「代表なくして課税なし」という言葉です。これは、アメリカ独立戦争のきっかけとなった、「強い意志」というものが込められています。自分たちの代表者がいないところで決められた税は、納める必要がない。私は、自らの代表が、国の支出のあり方を決めることと、自らが国を支える税金を負担しなければならないことは表裏一体であるということを知りました。
税金は私たちが生きていくための会費。とても身近なところに使われています。中学生には、3年間で約100万近い額が使われています。和歌山県民は、年間で約60万負担していることになります。昨年の台風12号による災害からの復旧・復興費も税金で負担しました。
現在は少子高齢社会です。これからどんどん高齢者が増えて、働き手が減っていきます。急速な高齢化に伴い、現在の社会保障水準を続ければ、国民負担率がさらに大きくなります。社会保障とは、私たちが安心して生活してくために必要な「医療」「年金」「福祉」「介護」「生活保護」などの公的サービスのことをいいます。将来に向けて社会保障制度を安定的に維持させるためには、制度の構造改革を進めていく必要があります。
豊かで安心して暮らせる未来のためには、公平な税負担と給付の関係について、わたしたち一人ひとりが考えることが大切です。