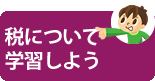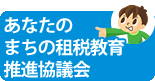私は、中学校の頃から「税金」について学習をしてきて、「税金とは、国民が国のために納めるお金であり、その使い道は国のため、あるいは国民のためにある」と学びました。
例えば、警察・消防費や国民医療費、病院や公園などの公共設備の建設費用などは、私たちの納める税金によって賄われており、そのおかげで私たちはさまざまなサービスや支援を平等に受けることができます。だから、「税」という制度が無くなってしまうと、今までお金を払わなくてもよかったことにもお金を払わなければいけなくなったり、今まで国が負担してくれていた分の費用もすべて自己負担になってしまったりするので、お金がない人は今まで受けられたサービスが受けられなくなるかもしれません。こうなってしまうと、「平等」とは言えません。
つまり、「税」とは私たちが平等に生活していくために私たちの暮らしを支えているのです。だから、「税金を納める」という行為は、私たちが平等に生活をしていく上で重要な行為であり、憲法にも国民の義務の一つとして「納税の義務」が定められています。
そのため、私たちの身の周りでは、あらゆるものに税金がかけられています。一番身近なものでは、消費税やたばこ・酒税、所得税などがあり、特に「消費税」は、学生の私たちにも関わりのある税です。たばこ・酒税、所得税に関しては、主に大人に関わりのある税です。こうして見ていくと、大人はもちろん、学生、つまり子どもにも税に関わる機会はあるということが分かります。これは、例えば六歳の男の子や女の子であっても、八十歳の老人であっても、「納税者」として認められるということになります。私たちの身の周りには、「納税者」が沢山いるのです。もちろん、私たち自身も「納税者」であるわけですが、その中で納税者としての自覚を持って税金を納めている人はどれくらいいるでしょうか。何気なく、又は何も考えずに税金を払っているという感覚の人が多いのではないでしょうか。そのため、「税金なんていらないじゃないか」と思っている人もいるでしょう。
しかし、「税金が私たちの暮らしに深く関わっていて、社会を成り立たせている」ということを理解し、その税金を自分が納めているという自覚を持っていれば、「税」の役割の大きさが実感できるのではないでしょうか。
この「納税者としての自覚」を一人一人が持ち、自分なりに「税」を考えることができれば、私たちは「納税者」であると言えるでしょう。そして、納税者であることは、「納税の義務」を果たしていることになるのではないかと私は思います。